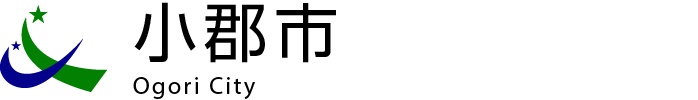所信表明 令和7年6月
はじめに
さて、この度の改選では、市の未来を市民の皆様に考えていただき、投票するという大事な機会がありませんでした。
そこで、小郡市議会6月定例会の開会に当たり、市民を代表する議員の皆様に、これからの市政の考え、私の3期目就任の所信を述べさせていただきます。
市民・地域・行政・民間がつながり、潜在能力が解放され、さまざまな施策が動き出した小郡市は、いま新たな成長のチャンスを迎えています。
1 未来へのまちづくりへ動き出します
これからのエリアビジョンを示し、市民と共有することは重要であると考えます。大きく3つのエリアの取組みを示します。
まず、宝満川左岸の立石校区エリアでは、筑後小郡インターチェンジ周辺まちづくり構想を具体化していきます。
この構想は、コストコ小郡倉庫店の出店により大きく動き出しました。定住人口の受け皿となる生活にぎわいゾーンを手始めに、さらなるにぎわいや雇用を誘導する面的整備推進ゾーン、花立山や旅籠油屋の交流ゾーンなど、各ゾーンの方向性をより具体的に示しながら、エリアの魅力創出を目指します。
2つ目のエリアは、小郡鳥栖南スマートインターチェンジ周辺エリア、まちづくり構想を推進します。交通の要衝を生かした土地利用と治水対策を一体化した開発のビジョンを示します。
両まちづくり構想の推進に当たっては、市と地域・地権者や民間事業者との三位一体により行っていきます。
3つ目のエリア、宝満川左岸地域の移住・定住と振興のための施策に取組みます。農業を基盤とした地域での少子高齢化や特有の産業構造に起因する人口減少が課題となっています。これに対して、地域未来投資促進法による土地利用の検討をはじめ、さまざまな農業関連資本の誘導、スマート化や交流人口を生かし多様な農業・産業振興を図ります。元気な農産業と豊かな自然環境、そして子育て・教育環境を基盤にした新たな移住・定住策について、内閣府から派遣された地方創生伴走支援員のサポートを受け、国が検討しているふるさと住民登録制度をはじめ、交流・関係人口増、移住定住促進策など、まず、少子化に歯止めのかからない味坂地域での対策からつくり上げます。
2 誰もが住み心地の良いまちづくりへ動き出します
人と人がつながる共生社会を目指すためには、安心して暮らせる環境づくりが大事です。
まず、NOハラスメント社会の目標を掲げ、今年度中に市民の皆さんをハラスメントから守り、ハラスメントの無い小郡市とするための条例を制定し、市民相談窓口の設置などの取組を行います。
また、DVや家庭内暴力、虐待などについても、引き続き、対応の充実・強化を図っていきます。
誰一人取り残されない共生社会の実現を目指し、超高齢社会の進展や経済格差などに伴う、高齢者や障がい者、生活困窮者等の社会的弱者が抱える課題に総合的に対応するため、重層的支援体制整備事業を本格的に実施していきます。事業を強力に推進するために、市役所と関係機関による連携と共働の枠組みで組織体制の強化を図っていきます。
さらに、高齢者・障がい者等要支援者の見守り事業を自治会や校区まちづくり協議会などとの共働事業で取組みます。
子どもや高齢者の居場所づくりの課題解決に向けては、幅広い世代の拠り所が必要であると考えます。その交流の場として、これからの図書館のあり方を検討していきます。
また、共生社会の実現の一環として、聞こえに不自由さがある方への理解と環境整備のために、小郡市手話言語条例を制定します。
3 子育ちに良いまちづくりへ動き出します
妊娠出産期から幼稚園・保育園、さらに小中学校と切れ目のない、こどもを中心とした子育ち環境づくりを行ってきました。さらなる取組の充実を図ります。
待機児童の解消を図るために、さらなる保育の受け皿の確保に向けて、着実に保育園の新設を進めます。
こども誰でも通園制度に向けては、市内保育所の園庭開放を活用するなど、保育協会と連携して取組んでまいります。
さらに、就学前の児童の幼児教育・保育の「質」の向上のために、インクルーシブ保育を推進します。各保育所が多様な子育てニーズに応えることができるように共通の学び合う仕組みをつくります。
そして、発達に課題のある就学前の児童を必要な支援につなげるため、5歳児健診のあり方について検討します。
子どものいる世帯の家庭の負担が重くなってきていますが、18歳までの医療費助成の拡充と拡大を図り、支援していきます。
大きな社会課題となっている、さまざまな理由で通学できない児童生徒のために、家庭や学校以外の第三の学び場づくり構想を検討し、中学校卒業後の進路から就職までを見据えた仕組みをつくります。
こどもまんなか社会の推進のため、「小郡市こども計画」に掲げる主旨をふまえ、子ども施策の基本理念となるこどもの権利条例を制定します。
4 災害対策による安心して暮らせるまちづくりへ動き出します
平成30年から毎年のように発生している浸水被害やいつ起こるかわからない地震など安心・安全なまちづくりは、まちづくりの前提と考える重要課題です。
まず、多種多様な治水対策の一つとして、宝満川右岸地域の農地等の開発に対して、保水機能を調整池の容量で確保する小郡独自基準を施行します。
住宅浸水対策として、半固定、固定の排水ポンプを設置します。
使用用途がなくなった、ため池の調整池活用を検討していきます。
大地震など大規模災害での対策本部設置・救助活動・受援体制・インフラ代替措置など初動から復旧・復興までのガイドラインを策定します。
住宅密集地での火災が近年多発し、救急出動も急増しているため、三井消防署三国出張所の人員拡充を働きかけます。
5 公共施設リニューアルへ動き出します
大型公共施設の建て替えについては着実に進めていかなければなりません。建設費が高騰していく中で、新たな財源の確保など工夫をしながら取組みます。
三井消防署の建て替えを令和9年度に完成させます。また、名称を小郡消防署と変更することを久留米広域消防本部に求めていきます。
学校給食センターについて、令和8年度中に運用を行い、より一層の地産地消の取組を推進します。
新体育館について、アリーナ棟を令和9年度、多目的棟を令和10年度の完成を目指します。クラウドファンディングや企業版ふるさと納税などの活用で財政負担の軽減を図ります。
老朽化が喫緊の課題となっている市役所庁舎については、整備計画等の策定を行います。
6 新たな行政運営へ動き出します
人手不足の改善やワークライフバランスの実現などに向けて貴重な人財を有効に活用し、限られた財源を必要なところへ適切に充てていく、より洗練された自治体運営が求められていると認識しています。
まず、職員のモチベーション向上や人財育成の強化などを図るため、新たな人事評価制度を導入します。
そして、職員が本来注力すべきコア業務に集中し、これまで以上に市民福祉の向上につながる施策を実施できるように、ノンコア業務についてのDX化とアウトソーシング化を加速させます。
係の枠組みにとらわれず、その時々に取組むべき課の事業を効果的効率的に推進できるように、係制廃止による課職員の流動的な人財活用を推進します。
限りある財源を効果的に活用するためには、今求められている施策に財源を充てることが必要であり、サンセット方式による予算編成の仕組み導入で、ビルド&スクラップを推進します。
さらに、これからの施策・計画の検討において、市民の幸福感の向上とハード・ソフト事業の連関を客観分析した、ウェルビーイング指標を運用していきます。
おわりに
以上が3期目に取組んでいく主な政策です。今後、職員と十分に議論を行い、進捗管理ができる、より具体的なアクションプランにしていきます。
市民や議員の皆様の、理解をお願いし、所信表明といたします。